ADHDの特性を持つ子どもに対する治療は、薬による治療、薬を使わずに行う療育・教育的な支援と、大きくわけてふたつあります。
療育・教育的な支援には、保護者が子どもの特性を理解し、適切な対応を学ぶこと(ペアレント・トレーニング)や、子どもが生活しやすいように周りの環境を整えること(環境調整)、リハビリ(作業療法・理学療法・言語療法)、子どもが適切な言動を行えるように場面設定を行って対処法を身につけること(ソーシャルスキルトレーニング)などがあります。
このページでは、ADHDの特性を持つ子どもの治療について、具体的な内容をご紹介いたします。
ぜひ、これからの支援にお役立てくださいね。
※賛否両論ありますが、弊社では「発達障害やADHDは個性のひとつだという考えもあるため、たとえ医師が勧めたとしても、安易な精神系の薬の服用は慎重になったほうがよい」という考えのもとサイト作りを行っています。薬につきましては、自己責任においてご利用ください。
ADHDを持つ子どもに対する治療とは
 ADHDの特性を持つ子どもに対する治療は、「衝動性、多動性、不注意を完全に治しましょう」というものではありません。
ADHDの特性を持つ子どもに対する治療は、「衝動性、多動性、不注意を完全に治しましょう」というものではありません。
薬物治療によって特性による困りごとを抑えることはできますが、完全に治すことはできません。
生活を行いにくくしている特性を薬物治療によって抑えることと、保護者や子ども自身がどのような特性があるのかを知り、そのうえで、日常生活が上手くいくように必要なスキルを身につけること、生活を行いやすいような環境に整えることを療育・教育的な支援によって行います。
決して「大人の言うことを聞くよい子」「注意されるような目立つことをせずに無難に過ごす子」「自分の意志は思い留めて周りに合わせられる子」にするのではありません。
自分の好きなこと、やりたいことには一生懸命に取り組み、自分らしさを持って生活し、充実した毎日を送れるようになることが大切なのです。
治療方法
薬物治療
 主な薬は、一般名:アトモキセチン塩酸塩(製品名:ストラテラ)と、一般名:メチルフェニデート徐放剤(製品名:コンサータ)、そして一般名:グアンファシン塩酸塩徐放錠(製品名:インチュニブ)の3種類。
主な薬は、一般名:アトモキセチン塩酸塩(製品名:ストラテラ)と、一般名:メチルフェニデート徐放剤(製品名:コンサータ)、そして一般名:グアンファシン塩酸塩徐放錠(製品名:インチュニブ)の3種類。
アトモキセチン塩酸塩(ストラテラ)はゆっくりと作用し、比較的副作用が少ないといわれています。
メチルフェニデート徐放剤(コンサータ)は中枢神経に作用し(そのため、不眠や食欲低下、頭痛、吐き気などの副作用がみられることもあります)即効性があり、12時間程度作用が続きます。
グアンファシン塩酸塩徐放錠は主に、メチルフェニデート徐放剤(コンサータ)だと強すぎるが、アトモキセチン塩酸塩(ストラテラ)だと効果を感じないといった子どもに勧められます。
ADHDは、満足感や達成感をじゅうぶんに得るための脳機能が低下していると考えられており、下記のような能力に問題が生じると言われています。
- 行動を先読みし優先順位をつけて計画的に行う能力
- ふたつのことを同時に行う能力
- 感情やモチベーション、覚醒などを調整する力
- 会話をイメージして自分の中に受け入れること
これらの脳の働きには、神経伝達物質であるドーパミンとノルアドレナリンが関係しています。
- アトモキセチン塩酸塩(ストラテラ)は主にノルアドレナリンを増加させる薬
- メチルフェニデート徐放剤(コンサータ)は主にドーパミンを増加させる薬(神経機能を活性化して、注意力の向上や行動・感情のコントロールを行いやすくします)
それぞれの薬の特徴は、車に例えていうならば、アトモキセチン塩酸塩(ストラテラ)はエンジンを長く働き続けられるようにする作用があり、メチルフェニデート徐放剤(コンサータ)はエンジンを力いっぱいかけて速く走る作用があります。
療育・教育的な支援では対応が難しいケースなど、医師が薬を用いたほうが良いと判断した場合には早期に薬物治療を開始します。
薬を服用し、特性による困りごとが抑えられて生活が上手くいくようになることで、本人に自信がつき、周りとの関係もよくなれば薬を用いた治療は終了することもあります。
薬は効果がある反面、副作用もあります。
保護者がしっかりと服薬管理をしなければならないため、主治医とよく相談し、納得したうえで薬での治療を開始することが大切です。
☝[参考に]ADHDと投薬治療について考える~おとなの場合、子どもの場合~/「息子の命を守りたい」~私がADHDの息子に薬を使い始めたきっかけ
療育・教育的な支援
 療育・教育的な支援には、次のようなものが挙げられます。
療育・教育的な支援には、次のようなものが挙げられます。
- 基本的な身体の動きや身体の使い方などを運動や活動を通して学ぶ理学療法・作業療法
- コミュニケーション面の支援を行う言語療法やソーシャルスキルトレーニング
- 保護者と子どもの対応・関係性について学ぶペアレントトレーニング
- 学校や家庭の環境を生活しやすいように整える環境調整
ひとつずつ詳しくご紹介します。
理学療法・作業療法

- 理学療法:基本的な「座る」「立つ」「歩く」「走る」などの動作や姿勢を保つことを獲得するための支援
- 作業療法:食事・着替えなどの生活に必要な動作や工作や絵を描くなどの机上活動、なわとびなどの協調性が必要な運動を獲得するための支援
「座る」「立つ」姿勢を保つための筋力が弱いなどの場合は理学療法が選択されますが、歩き、走れるADHDの子どもは理学療法よりも感覚面や認知面も含めて複雑な動作や活動をみる作業療法が選択されることが多いかもしれません。
作業療法では、実際に身体を動かす場面や道具を手で操作する場面をみながら、身体の使い方や運動面・認知面での評価を行います。
「どのようなところが難しいか」「どのようなことが得意か」を見つけ、苦手な部分を克服するために必要なことを身につけられるような支援や、得意なことをうまく活用できる支援を行っていきます。
例えば、ボールや平均台、トランポリンなどの道具や遊具を利用して上手くバランスをとることや、自分の身体の動きをイメージして運動を行うこと、また、工作やカードゲームなどの遊びを通して机に向かって活動すること、手と目の協調性を促すこと、次の工程を想像しながら活動を実践することなどを行っていきます。
個別でセラピストとマンツーマンで行う場合と、何人かの集団で同じ運動や活動を通して行う場合とがあります。
大切なことは、活動を通して自ら考えて実行し、自尊心や達成感を得ることです。
言語療法
 言語療法は「発音」「発話」「言葉の理解」「読む」「書く」などのコミュニケーション面の支援を行います。
言語療法は「発音」「発話」「言葉の理解」「読む」「書く」などのコミュニケーション面の支援を行います。
絵カードやプリント教材、遊びを通してことばの発達を促し、どのような働きかけを行えばコミュニケーションが行いやすいのかなどのアドバイスも行います。
また、唇の動きや舌の動きに問題がある場合は口腔機能の練習を行うこともあり、飲み込みや食事の支援も行います。
ソーシャルスキルトレーニング
 社会的スキル訓練、社会生活技能訓練などとも呼ばれ、認知行動療法のひとつに位置づけされています。
社会的スキル訓練、社会生活技能訓練などとも呼ばれ、認知行動療法のひとつに位置づけされています。
日常生活で出くわす場面設定を行い、「こんなときはどうするか」という対応を学びます。
例えば、「学校の隣の席の友達が消しゴムを忘れて困っています。あなたはどうしますか?」という設定に対する自分の対応の仕方を考える、など。
ひとつの設定に対して一人ひとりが応えていく場合や、ゲームの中に取り入れて行う場合、図や絵にかいて考える場合、実際にその場面を演じて行う場合などがあります。
他にもひとつのストーリーを紙芝居や映像でみて、登場人物の行動に沿って「あなたならどうしますか」という対応を考えていくことを行うこともあります。
実際の場面を想定して行うことで、生活場面で同じようなことが起こった場合に、適切な対応を行えるようになります。
また、課題に取り組むことでルールを守ることや集中力を養うこと、集団での活動によって他の人との関わりを学ぶこと、場を共有すること、認める・ほめることで自尊心を高めることが促されます。
子どもにとって「こういうときはこうすればいいんだ」という対応の仕方の引き出しを増やしておくことで、日常生活を過ごしやすくなります。
ペアレントトレーニング
 ペアレントトレーニングとは、保護者が子どもと一緒に、生活の中で起こる様々な問題への対応の仕方を学んでいこうというプログラムです。
ペアレントトレーニングとは、保護者が子どもと一緒に、生活の中で起こる様々な問題への対応の仕方を学んでいこうというプログラムです。
ペアレントトレーニングでは、日常生活の中でよく起こる「こういった場面ではどのように対応するべきか」ということを、子どもの行動とそれに対する保護者の対応をともに学んでいきます。
📌例「駅の階段を駆けあがり、ホームで走り回る」という行動に対して
- 子どもの後を追いかけて「こら!走らないの!」と怒鳴るのではなく、出掛ける前に「駅に着いたら階段があるけれど、一緒にのぼるから階段の下で待っててね」とルール、約束事をつくっておく。
- 駅に着いたときに「階段があるね、一緒にのぼろうと約束したよね」と声をかけることで、子どもは走らずに待つことができる。
- 約束したことを子どもが守れたら、しっかりと褒めてあげる。
「こら!走らない!」と言われても子どもには「怒られた」という記憶しか残らず、自尊心も傷ついてしまいますが、事前に約束したことを守ることができ、そして保護者が子どもを褒めてあげるとそれが自信に繋がり、次も同じように行動しようというモチベーションも高まります。
どのようにほめるのか、どのような声掛けをすればよいのかという具体的な方法を学ぶことができるため、日常生活に応用することができます。
ペアレントトレーニングでは、保護者も子どもも穏やかな生活が送れること、笑顔で過ごせる時間が増えるための生活の中の対処法を学びます。
環境調整
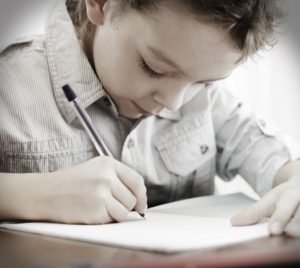 子どもが家庭や学校で過ごしやすいように環境を整えることを行います。
子どもが家庭や学校で過ごしやすいように環境を整えることを行います。
ADHDの特性を持つ子どもの「注意が散漫してしまう」という困りごとには、外からの情報が入り過ぎてしまっていて、どれに注目してよいのかがわからないということもあります。
そのような場合は、机のまわりにパーテーションを置いて周りからの情報を少なくすることで作業に集中しやすくなることがあります。
また、見通しを立てやすくするためにタイマーを用いることや、行うべきことを絵カードでわかりやすく示すなど、子どもが行動しやすいように工夫をします。
学校と家庭との関わりを同一に保つために、学校の先生に机の位置や声掛けの仕方など、配慮してほしいことを伝えることも有効です。
その他の治療
 他にも、サッカーなどのスポーツを仲間と一緒に行うことや、音楽を通して身体の協調性や感覚情報の統合を促す音楽療法、そして食事療法などのアプローチもあります。
他にも、サッカーなどのスポーツを仲間と一緒に行うことや、音楽を通して身体の協調性や感覚情報の統合を促す音楽療法、そして食事療法などのアプローチもあります。
サッカーなどの有酸素運動は脳を活性化します。
スポーツを行うことで自然と運動の機会がつくられ、仲間とともにスポーツを楽しみ、ルールを守ることや規律も学べます。
コートの中でどのように動くかという非言語的なコミュニケーションや、チーム内のメンバー同士でのコミュニケーションも促すことができます。
食事療法では、「栄養バランスのとれた食事を摂り、糖分や添加物の摂り過ぎは避け、ビタミン・ミネラルの含まれた緑黄色野菜や海藻などを積極的に食べるようにする」といった内容がなされます。
音楽療法では音楽を「聴く」「歌う」「音楽に合わせてリズムをとる」「楽器を演奏する」などを通して、「聴く情報」と「身体を動かす情報の協調を促すこと」や「表現のバリエーションを増やすこと」「周りと合わせること」などを促していきます。
☝[参考に]発達障害児を育てる親御さんへ~療育で作る子どもの未来~
まとめ
 ADHDの特性を完全に治すことはできませんが「環境を整えること」「声掛けを行うことなどの工夫」「活動を通して運動を行うこと」「身体の使い方」「身体の協調性」「コミュニケーションを促すこと」を通して困りごとに対しての対処法を学び、日常生活を過ごしやすくすることができます。
ADHDの特性を完全に治すことはできませんが「環境を整えること」「声掛けを行うことなどの工夫」「活動を通して運動を行うこと」「身体の使い方」「身体の協調性」「コミュニケーションを促すこと」を通して困りごとに対しての対処法を学び、日常生活を過ごしやすくすることができます。
治療法は色々ありますが、「今、子どもに必要なものは何か」ということを主治医とよく相談して選びましょう。
いくつかの治療を併用する場合もあります。
「子どもができることを達成して自信をつけること」「子どもが自ら考え行動できるようになること」「子どもも保護者も充実した日常生活を送れること」を目指して治療は行われます。
それぞれ専門的な知識・技術を持ったスタッフが、子どもの特性をしっかり把握したうえでアプローチを行いますので、気になることやわからないこと、困ったことがあれば、その都度相談していきましょう。
必要であれば、家庭と学校との連携なども治療の経過で提案されます。
治療の場を有効に活用して、子どもも保護者も過ごしやすい環境をつくっていきましょう。


















コメント