小児神経科などで診断を受けて「自閉症スペクトラム」だとわかったとしても、診断名だけでは子どもが抱えている障害の内容や程度を正確に把握できず、適切なサポートはできません。
発達に遅れがある子どもや障害がある子どもにとって、本当に必要なものは診断名ではなく、「どうすれば日常的に感じる不便さ・不都合さが減るのか」という具体的な対応策です。
今回は、この対応策を探り、見付けるのに役立つWISC-IV知能検査の概要と結果の見方をご紹介します。
WISC-IV知能検査の概要
 子どもの発達の程度を知る検査には、WISC、K-ABC、田中ビネー知能検査、SM式社会生活能力検査、新版K式発達検査など様々なものがあります。
子どもの発達の程度を知る検査には、WISC、K-ABC、田中ビネー知能検査、SM式社会生活能力検査、新版K式発達検査など様々なものがあります。
それぞれ受けられる年齢や結果として出てくる項目が異なっており、目的に合わせて検査を受けます。
今回ご紹介するWISCは、未就学児から受けることができ、指導者や親が子どもの特性を理解しやすく、サポート方法を考えやすいという特徴があります。
知能ってなんのこと?
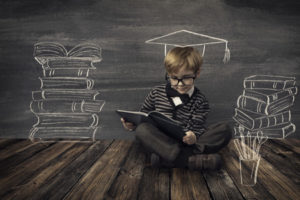 【知能】というと誰もが「勉強がよくできること」だと思いがちですが、(確かに【知能】には学習をして知識を増やし、問題を解いていく能力も含まれていますが)それだけではありません。
【知能】というと誰もが「勉強がよくできること」だと思いがちですが、(確かに【知能】には学習をして知識を増やし、問題を解いていく能力も含まれていますが)それだけではありません。
言葉はもちろん、言葉以外の目に見える情報を正確に読み取る能力や、目に見えないもの(感情や場の空気、行間など)を把握して適切な行動を取る能力、初めての場所や新しい環境に適応する能力も知能に含まれます。
WISC-IV知能検査は一度の検査で幅広い知能について検査ができ、どの能力がどれくらいのレベルなのかを知ることができます。
検査を受けられる年齢
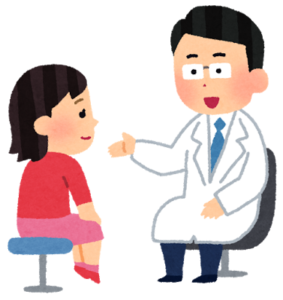 WISCはいくつかバージョンがあり、現在よく行われているWISCは「WISC-IV」という検査です。
WISCはいくつかバージョンがあり、現在よく行われているWISCは「WISC-IV」という検査です。
WISC-IVは、5歳0ヶ月~16歳11ヶ月までの子どもが受けられます。
就学前の子どもが就学先を判断するために受けたり、就学中の子どものつまずきを把握することに利用したり、子どもの成長度合いを把握することにも活用されます。
検査は、検査を実施する人と検査を受ける子どものみで実施され、原則、親は同席しません。
ひとりでイスに座り、検査を実施する人と一対一で課題に取り組めることが前提です。
人見知りや場所見知りが激しかったり、検査が終わるまで室内に居られないような場合は、検査を実施できなかったり、途中で終了となります。
検査を受けられる場所
 WISCは病院、自治体などが運営している発達支援センター、民間の発達支援施設などで受けることができます。
WISCは病院、自治体などが運営している発達支援センター、民間の発達支援施設などで受けることができます。
検査を実施できる人は、医師や臨床心理士・言語聴覚士といった専門家(WISCの講習会などを受けた実施技術を持つ人)です。
筆者の娘は5歳のときに民間の塾で臨床心理士による検査を受け、7歳のときに言語聴覚療法を受けている病院で言語聴覚士による検査を受けました。
発達診断は医師でなければできませんが、WISC-IV知能検査は医師以外の人でも専門家であれば実施できます。
未診断でも検査は受けられるので、専門医の診察を待っている間に親が子の特性を把握することができます。
検査にかかる時間と費用
 WISCの検査はだいたい40~60分ほどで終わりますが、子どもの体調や特性によって必要な時間は変わり、場合によっては最後まで課題を終える前に終了するケースもあります(この場合、日を改めて実施するか、検査を断念するか、それは実施者や親の判断になります)。
WISCの検査はだいたい40~60分ほどで終わりますが、子どもの体調や特性によって必要な時間は変わり、場合によっては最後まで課題を終える前に終了するケースもあります(この場合、日を改めて実施するか、検査を断念するか、それは実施者や親の判断になります)。
費用は検査を受ける場所で異なり、無料~数万円程度になります。
大きな差なので、どこで受けるか事前に調べておくとよいですよ。
検査費用の例
- 自治体などが運営する発達支援センター、教育センター:無料
- 総合病院などの公的病院:保険適用となる(三割負担なら1,350円)
- 民間施設:数万円。
私の娘の場合、塾で検査を受けた時は一万円でした。
(臨床心理士による検査費と、検査結果の解説書類を合わせた金額)
病院で検査を受けた時は200円でした。
(医師の診察を受けてから言語聴覚士の検査を受けたため、保険適用で三割負担、ここに自治体が実施する「子どもの医療費助成制度」が適用されて200円になりました)
この時もらったもの(結果)は、解説書のない数値が書かれた紙だけでした。
なるべく安く受けたい!と思うかもしれませんが、発達支援センターや公的病院は検査の予約を取ること自体が難しいケースが多く、希望してから検査を受けるまで数ヶ月~数年待ちだということも珍しくありません。
その点、民間施設の場合は比較的柔軟に検査日程を組んでもらえます。
検査結果の必要性に応じて検査を受ける場所を変えるとよいですね。
なお、検査結果に関する詳しい解説書や、診断書をもらうとなると別料金が必要になります(この別料金は発行する人(施設)によって異なります)。
WISC-IV知能検査の内容は非公開
 「子どもがどんな検査を受け、どういう受け答えをしているのか知りたい!」という親は私を含め多くいますが、残念ながらWISC-IV知能検査の内容は非公開です。
「子どもがどんな検査を受け、どういう受け答えをしているのか知りたい!」という親は私を含め多くいますが、残念ながらWISC-IV知能検査の内容は非公開です。
また、一度検査を受けるとWISCは二年前後の間隔をあけなければ再度受けることはできません。
「検査の結果が不本意だから」だと思っても、簡単に受け直すことはできないので、注意をしましょう。
短期間に繰り返し検査を受けると子どもは問題を覚えてしまい、正しい結果が得られなってしまいますので「知りたいから」といって、しつこく検査実施者に問題を聞くことはしないでくださいね。
WISC-IV知能検査の結果からわかること
子どもの位置がわかる
WISCの検査では、発達について子どもの位置(同じ年齢の子どもと比べた場合、その子が平均くらいなのか、平均より知能が高いか低いか)がわかります。
- IQ100:平均値
- IQ80~120:平均内レベル
- IQ70~79:グレーゾーン(境界線)
- IQ69以下:軽度の知的遅れ
- IQ40以下:WISCでは測定できない(重度の知的な遅れ)
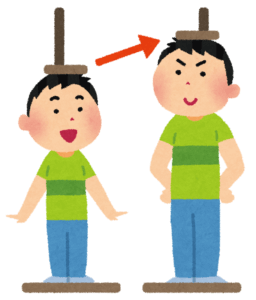 5歳で検査を受けた時に結果がIQ65であれば、5歳の子どもの平均よりも知的に遅れており、それも、軽度の知的遅れと判断されるレベルとなります。
5歳で検査を受けた時に結果がIQ65であれば、5歳の子どもの平均よりも知的に遅れており、それも、軽度の知的遅れと判断されるレベルとなります。
8歳で検査を受けた時に結果がIQ90であれば、8歳の子どもの平均であり、知的な遅れはないと判断されます。
このように、間を置いて検査をすると「前は知的な遅れあり、と判断されるレベルだったのに、平均レベルまで成長した」ということなどがわかります。
今、結果が悪くても数年後にはグッと伸びていることもありますから、結果に一喜一憂する必要はありません。
項目別の知能がわかる
WISCでは複数のIQが出されます。
- 言語理解(VCI)のIQ:語彙力や言葉を聞いて理解する能力のこと
- 知覚推理(PRI)のIQ:見たものを把握して理解する能力のこと(左にある図形を見て右側の図形を完成させることや、左右の絵の間違い探しといった言葉以外のものを理解する能力)
- ワーキングメモリー(WMI)のIQ:一時的な記憶能力や、注意力、集中力のこと
- 処理速度(PSI)のIQ:目で見たものを速く正確に処理する能力や、文字などを書く能力のこと
この4つの項目のIQと、全検査IQ、合計5つのIQが結果として得られます。
単なるIQだけでなく複数の知能に関して結果が出るので、どの知能にどんな特性があるのか、全体として平均的なのか凸凹があるのか把握することができます。
知能の凹凸を把握できる
 WISCの検査を受けると、知能の凹凸(できること、できないことの差が大きい状態)を把握することが可能になります。
WISCの検査を受けると、知能の凹凸(できること、できないことの差が大きい状態)を把握することが可能になります。
例えば、IQ85といっても4つの項目が全て80~89の範囲内に治まっているIQ85もあれば、IQ100とIQ70の項目があるIQ85があります。
後者の場合、できる・できないの差が大きいですよね。
筆者の娘の場合
- 5歳の時のIQは70でしたが、細かく項目を見るとIQ76の項目とIQ68の項目があり、できること・できないことの差が大きいため、それに応じたサポートが必要(できないことを重点的にサポートしてあげれば、知能全体が上がっていく可能性がある)とわかりました。
- この結果をもとに療育を続け、7歳でもう一度検査を受けた時にはIQ80という結果が出ました(IQ76だった項目はIQ78でしたが、IQ68だった項目はIQ94でした)。
2年間でめざましい伸びをみせてくれた娘ですが、できること・できないことの差が大きいという特徴は残っており、4つの項目のIQから出された全検査IQが70(境界域)からIQ80(平均内)に伸びたから「サポートがいらない子になった」というわけではありません。
確かに数値上は平均になりましたが、知能に凸凹がある子であり、できないことに対してサポートを続けていかないといけない子です。
こうした特徴を把握できることがWISCの大きな魅力です。
サポートの仕方が見えてくる
 WISCの結果を見ると、言葉の理解・図形や絵の把握・一時的な記憶能力・視覚情報の処理速度といった4つの項目の得意・不得意がわかります。
WISCの結果を見ると、言葉の理解・図形や絵の把握・一時的な記憶能力・視覚情報の処理速度といった4つの項目の得意・不得意がわかります。
言葉が苦手な子には絵を交えて説明・解説する、記憶することが苦手な子にはやることリストを作る、といったサポート方法が必要です。
さらに、算数の文章問題を教える時を例に挙げると、問題を図に書き出したり、ポイントになる数字などに線や丸を付けるといったサポート方法を教えることで、自力で解けるように導いていけます。
WISCの結果は子どもの得意な部分を把握し、それを使って苦手な部分をカバーする方法などを見付けていくことに役立ちます。
娘はワーキングメモリーや処理速度に比べて言語理解や知覚推理が低く、IQの差が15ほどあります。
検査を実施した専門家によれば「言葉の理解、ルールの理解が大きな課題。特定の言葉の意味を覚えればルールを理解し、解くことができると思われる。とりあえず、言葉を覚えることと、色々なルールの問題に当たって経験・記憶すれば対応していけるようになるだろう」ということでした。
「ドアの先にある迷路をクリアする能力はある。でも、ドアノブに手が届かない。このドアノブに手が届くようになれば課題はクリア!……ドアノブに手が届くまで成長を待つか、ちょうどいい高さの台を探して持ってくる、ということができるようになろう」……そんな感じです。
子どもに合った具体的なサポートを考える手段としてWISCは有効です。
WISC-IV知能検査の結果=障害ではない
 WISC-IVは子どもの特徴を把握するために有効な検査ですが、注意したいことは、WISCの検査結果として出されるIQが障害を証明するものではない、ということです。
WISC-IVは子どもの特徴を把握するために有効な検査ですが、注意したいことは、WISCの検査結果として出されるIQが障害を証明するものではない、ということです。
WISCはあくまで、複数の項目について同じ年齢の子と比較した場合にどの程度の知能があるか、判断する時の参考となる数値です。
WISCでIQが全て100以上だったとしても、人の気持ちを理解したり、場の空気を読んで適切な行動を取ることができないという障害もあります。
気を付けておきたい点
- 「検査の指示が理解できなくて解答できない(問題を解く能力は持っているけれど、ルールが解らなくて解けない)」ということがあるため、下記のようなことが起こり得ます。
- IQ90(平均内)であっても、IQ60(軽度の知的障害)の項目とIQ120(平均よりもできる)の項目がある人もいる。
- 自閉症の子どもなどに代表される「言葉の遅れ」を持つ子どもは、WISCの結果が低く出ることがある。
 WISCの検査では、問題を出す人は子どもの手助けができません。
WISCの検査では、問題を出す人は子どもの手助けができません。
問題自体を解く能力はもっている(具体例を示してもらったり、問題の言い方を変えてもらったら解ける)子であっても、検査の時、出題者は子どもに合わせた手助けができないため、能力はあるのに結果として出される数字が低くなる(知的障害があると判断される)ということに繋がるのです。
実際、筆者の娘は5歳の時に受けたWISCの結果がIQ70(IQ68の項目を含む)だったため、支援学級(知的学級)に在籍して小学一年生を過ごしました。
しかし、担任が「知的な遅れがあるとは感じられない(知的学級でサポートが必要な子ではない)」として、小学二年生で支援学級(自閉症・情緒障害特別支援学級)に転籍しました。
知的学級と情緒学級では受けられるサポートが違います。
WISCで特徴を把握したから、と言って、その結果が正しく子どもの困りごとを反映しているとは限らないのです。
WISCの結果はあくまで参考とし、子どもの実態に合わせて適切なサポートを実現していく必要があります。
まとめ
 WISC(今はWISC-IVが主流)知能検査は、複数の知能について検査ができ、知能の高い・低いだけでなく凹凸まで数字で把握することができます。
WISC(今はWISC-IVが主流)知能検査は、複数の知能について検査ができ、知能の高い・低いだけでなく凹凸まで数字で把握することができます。
子どもの特性が具体的な数字で表されるので、より正確なサポートを実現することに繋がります。
検査は医師以外にも、臨床心理士や言語聴覚士などの専門家が実施でき、さらに病院・教育センター・民間施設など様々な場所で検査が受けられます。
発達診断よりも手軽で早く検査を受けることができるので、より早くから始める療育に役立ちます。
しかし、結果として得られた数字=障害の証拠ではありません。
数字が平均だったから大丈夫、というわけでもありませんし、IQが軽度の知的障害だったからといって子どもに理解力がないわけでもありません。
複数の項目について出されたIQの数値はもちろん、点数が低かった項目について精査することが正確に子どもの特性を把握することに繋がります。
また、継続して検査を受けることで子どもの伸びや変化を把握することができます。
ただし、子どもが問題を記憶してしまわないよう、二年前後の間隔を開けて継続的に受けてサポート方法や特性把握に努めましょう。
特性を把握することは「何に注意すればいいのか」「どういう環境が子どもに合っているのか」といったことを判断することに役立ちます。
検査をすると、できる・できないが数字として表されてしまって怖い、と感じる人もいるかもしれませんが、その怖さ以上の重要な情報を得られる検査ですので、受けたことがない人は検査を前向きに捉えて暮らしの中に活かしていきたいものです。

















コメント