「うちの子、なんだか落ち着きがない……」「なんで言うことを聞いてくれないの?」「何だか他のみんなと違うのでは?」と感じたとき、可能性のひとつとして考えられるのが発達障害です。
では、発達障害って何なのでしょうか。
性格も発育のスピードも一人ひとり違いますよね。
他人とのコミュニケーションが得意な子もいれば苦手な子もいますし、何かに集中することが得意な子もいれば苦手な子もいますね。
それは一人ひとりの「個性」であり、違っていて当然のこと。
しかし、そのような「個性」も、程度が大きければ日常生活に支障が生じることもあり、これを「発達障害」と呼んでいます。
今回は発達障害とはどういうものなのかに焦点をあて、また、診断結果を受け入れることの大切さについても詳しく解説していきます。
発達障害(自閉症スペクトラム/ADHD/LD)について
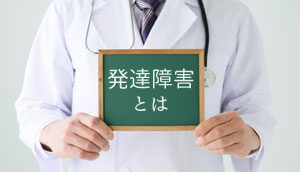 発達障害は、主に次の3つに分類されます。
発達障害は、主に次の3つに分類されます。
- 自閉症スペクトラム
- ADHD(注意欠陥・多動性障害)
- LD(学習障害)
発達障害児はおよそ15人に1人の割合で見られ、決して珍しいものではありません。
子どもが保育園や幼稚園に通うようになって、集団生活を開始する3歳前後に気付かれることが多いと言われています。
📌自閉症スペクトラム
自閉症スペクトラムとは、自閉症と、それに類似しているアスペルガー症候群、知的障害を伴わない高機能自閉症などをひとまとめにしたもののことを言います。
主な特性は、対人関係やコミュニケーションが困難であることや、特定のものへの興味や音や光などに対する感覚に偏りがあることです。
📌ADHD(注意欠陥・多動性障害)
ADHDは注意欠陥・多動性障害ともいいます。
主な特性は、気が散りやすい「不注意」、落ち着きのない「多動性」、我慢ができない「衝動性」の3つがあります。
それぞれの特徴の現れ方によって、物忘れが多くボーっとしているタイプや感情のコントロールができずにすぐカッとなるタイプなどが見られます。
📌LD(学習障害)
LDとは、知的障害ではないにも関わらず、読む・書く・話す・聞く・計算するなどのうち特定の能力の習得が困難であることを言います。
特に、LDの子の多くは読み書きが困難である「ディスレクシア」を抱えていると言われています。
一人で悩まないで専門家に相談を
 今この記事を読んでくださっている人は、定期検診などで発達障害の診断を受けたお子さんの親御さんやご家族、子どもの教育に携わっている人など、様々な形で発達障害と関わっている場合が多いことでしょう。
今この記事を読んでくださっている人は、定期検診などで発達障害の診断を受けたお子さんの親御さんやご家族、子どもの教育に携わっている人など、様々な形で発達障害と関わっている場合が多いことでしょう。
もしくは、「自分の子どもはもしかして発達障害なのでは……?」「発達障害だったらどうしよう」という不安を持っている人かもしれません。
まずお伝えしたいことは、一人で悩み続けないでほしいということです。
子どもと関わる中で「もしかして……」と感じたとき、多くの人はその特徴をインターネットで検索することでしょう。
そして、「ここに書いてある情報と似ているから、うちの子はADHDなのかしら」「でも、この情報と違う部分もあるからやっぱり障害ではないのかも」といったように一喜一憂してしまいます。
確かに、インターネットは簡単にたくさんの情報を得ることができて便利ですが、そこに書かれていることがすべて正しいというわけではありません。
発達障害の特性は一人ひとり異なる場合が多いため、書かれている情報とお子さんの特徴が必ず一致するとは限りません。
正しいかどうかわからない情報に振り回されずに、気になることがあったらまずは専門家に相談してみることが一番です。
悩みや不安がある時、どこに相談すると良いの?
 発達障害について専門としているのは、小児神経科や児童精神科などの医療機関です。
発達障害について専門としているのは、小児神経科や児童精神科などの医療機関です。
しかし、どこの病院に発達障害専門の医師がいるのかわからない場合や、いきなり精神科を受診するのに抵抗があるという場合、まずはお子さんが普段から診てもらっているかかりつけの小児科に相談してみてください。
小児科で発達障害を診てもらうことはできませんが、おすすめの専門医や医療機関を紹介してくれることもあります。
医療機関以外の相談先としては、地域の保健センターや子育て支援センター、発達障害者支援センターなどの機関もあります。
お子さんが保育園や幼稚園、学校に通っているのであれば、保育士や先生に相談し、園や学校での様子を聞いてみるのも良いでしょう。
専門家に相談した方が良いということはわかっていても、発達障害であるという診断を受けることが怖くてなかなか相談に踏み切れないでいるお母さんもいるかもしれません。
しかし、誰にも相談せずに一人で悩み続けても何も解決しませんし、何よりもお子さんのためになりません。
まずは勇気を出して、かかりつけの医師に相談してみましょう。
診断結果を受け入れることの大切さ
 お子さんが発達障害であると診断されたとき、それをすぐに受け入れることは簡単なことではないかもしれません。
お子さんが発達障害であると診断されたとき、それをすぐに受け入れることは簡単なことではないかもしれません。
思いがけない「障害」という言葉にショックを受けて頭の中が真っ白になってしまったり、「うちの子が障害を持っているはずがない!」「きっとそのうち変わるはずだ!」と診断を受け入れることを拒否したりする親御さんは少なくありません。
しかし、お子さんが発達障害であるということを受け入れ、どのような特性を持っているかをしっかりと理解することは、発達障害児と関わる上で非常に重要なことです。
📌文字を読むことが苦手なLDの子
文字をなかなか読むことができないのは決して努力不足などではなく、LDだからです。
それなのに、子どもがLDであることを受け入れず、「どうしてこんなこともできないの?」「頑張りが足りないんじゃないの?」と言って、これまでと同じ勉強方法を続けさせても、苦手を克服できるものではありません。
そればかりか、できないことを責められ続けた子どもは「自分はだめな子なのだ」と考えるようになり、勉強が嫌いになったり不登校やうつになってしまったりすることもよくあります。
📌すぐに友達に暴力を振るってしまうADHDの子
その子がすぐに相手に手を出してしまうのは、ADHDの特性のひとつである衝動性のためです。
それを理解せずにただ叱りつけても、暴力を振るうという行動が改善されることはありません。
そして、ADHDのことを理解されずに叱られ続けて育った子どもは、さらに反抗的になってしまいます。
場合によっては、反社会的な行動をするようになってしまうことも実際にあり得るのです。
発達障害を受け入れないで放置することは、何も解決しないばかりか不登校やうつ、問題行動を引き起こすことにも繋がってしまいます。
発達障害による特性は、支援を工夫することで改善することのできるものなのです。
視力が低下しているとわかったら眼鏡をかけるように、発達障害の診断を受けたら、子どもがどのような特性を持つかをしっかりと受け入れて、適切な支援を行うことが大切です。
医師からお子さんが発達障害であると診断されたときにそれを受け入れることは、お子さんに障害者のレッテルを貼ることでもお子さんの将来を諦めることでもありません。
診断を受け入れることが、より良い日常生活を送れるための正しいスタートになるのです。
発達障害は親の育て方が原因ではない
 もうひとつ、お子さんが発達障害であるとわかったときにお伝えしたいことがあります。
もうひとつ、お子さんが発達障害であるとわかったときにお伝えしたいことがあります。
それは、発達障害は親の育て方が原因ではないということです。
子どもが発達障害であるということを知ると、「私の育て方が悪かったのだろうか?」と親御さんがご自身を責めてしまうことがよくあります。
また、発達障害のことをよく知らない他の親御さんたちや周りの人たちから、「あなたの育て方が悪いから子どもがそんなふうになるんじゃないの?」という心無い言葉をかけられることもあるかもしれません。
しかし、発達障害は親の育て方のせいで起こるものではありません。
発達障害は脳機能の発達に偏りが見られる障害です。
脳には思考や記憶、言語理解、感情、身体反応などをコントロールする働きがあります。
発達障害は、そのような働きを持つ脳や脳に情報を伝える神経伝達物質の働きに偏りがあることで起こる、生まれつきの脳機能障害の一種です。
お子さんが発達障害を持っているのは、決してあなたの育て方が悪いわけでも、他の親御さんよりも頑張りが足りないわけでもありません。
「私の育て方のせい?」と悩んでしまう親御さんは、きっとこれまで人一倍一生懸命に子育てをしてきたはずです。
どうか、ご自身を責めないでください。
自信を持って子育てをしてくださいね。
育てかたで子どもは変わる!
 発達障害は親の育て方が原因で起こるものではありませんが、育て方は発達障害児の成長に大きく関わる非常に重要なものです。
発達障害は親の育て方が原因で起こるものではありませんが、育て方は発達障害児の成長に大きく関わる非常に重要なものです。
間違った育て方を続ければお子さんの成長に悪影響を与えてしまうこともありますし、反対に、適切な育て方によって発達障害による特性を改善することだってできるのです。
では、どのような育て方が発達障害による行動や特性の改善に効果的なのでしょうか。
ここでまずお伝えしておかなければならないのは、「ADHDの子どもはこう育てる」「LDを改善するためにはこの育て方をすれば良い」といったマニュアルはないということです。
なぜならば、ADHDといっても集中することが苦手な子もいれば衝動的な行動をする子もいるように、同じ発達障害でも一人ひとり特性が違うためです。
また、ADHDと自閉症スペクトラムの両方の特性を持つなど、2種類以上の発達障害を併せ持つ子も珍しくありません。
そのため、ADHDやLD、自閉症スペクトラムなどの診断名よりもその子の特性に応じて、一人ひとりその子に合った支援を行う必要があるのです。
すぐに気が散って学習に集中できない子どもには
 まずは、机の上をきれいに整頓し、テレビなどを消して雑音が耳に入らないようにして、子どもが集中できる環境を整えてあげることから始めましょう。
まずは、机の上をきれいに整頓し、テレビなどを消して雑音が耳に入らないようにして、子どもが集中できる環境を整えてあげることから始めましょう。
そして、子どもの集中力の持続時間に合わせて休憩を入れながら学習に取り組ませましょう。
最初は5分間や10分間のような短時間しか集中力が続かない子もいるかもしれません。
しかし、集中力がないのは本人にやる気がないためではないので、集中できないことを責めてはいけません。
「10分間しか集中できない」と叱るのではなく、「10分間も集中できたね!」とお子さんをしっかりと褒めてあげましょう。
褒められることで子どもは達成感や自己肯定感を得ることができます。
また、子どもの集中力を持続させるために、好きな学習から先に取り組ませたり、決められた時間集中して学習できたらごほうびをあげたりするというのも良いでしょう。
それから、子育ては親御さんが一人で行うものではないということも忘れてはいけません。
いくら親御さんが子育てを頑張っても、子どもと関わる他の大人たちが発達障害について理解せずに間違った対応を続けてはその子にとってよくありません。
お子さんの発達障害について夫婦や祖父母、保育園や幼稚園、学校などの先生がきちんと理解し、連携して子育てをすることが大切です。
おわりに
 ここまで、これから発達障害と向き合っていく親御さんに最初に知っておいてほしいことをお伝えしてきました。
ここまで、これから発達障害と向き合っていく親御さんに最初に知っておいてほしいことをお伝えしてきました。
まだまだ発達障害を持つ子どもを育てることに不安を感じている親御さんもおられることでしょう。
ただでさえ子育ては大変なのに、子どもが発達障害を持つとなると、なおさら慣れないことばかり。
毎日が失敗と試行錯誤の連続です。
最初はなかなか上手くいかず、どうすれば良いのか悩むことも多いでしょう。
子育てを頑張ることは大切ですが、ずっと頑張りすぎると疲れきってしまいますよね。
周りの人の手を上手に借りたり信頼できる人に相談したり、たまには息抜きすることだって必要です。
子育てに正解はありません。
発達障害の有無にかかわらず、子育てをする上で最も大切なものは、子どもに対する愛情です。
親御さんがお子さんのことを大切に思っているということや、愛しているということを言葉でしっかりと伝え、たくさん抱きしめてあげてください。
親御さんからの愛情は必ずお子さんに伝わり、お子さんの成長に必ず良い影響を与えてくれますよ。


















コメント